【中間・期末テストで高得点を取りたい】中学生の定期テスト対策を徹底解説
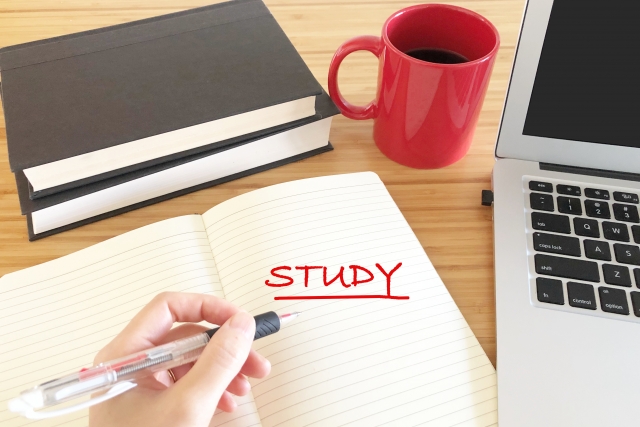
小学生と中学生で大きく変わる点は、定期テストがあることです。
公立の中学校では、年5回の定期テストがあります。
小学校の時の単元テストとは違い、範囲が広いのでしっかりテスト対策しておかないと、なかなか良い点が取れません。
また、定期テストの結果は通知表の評価や高校の進学を考えたときに重要となる内申点にも影響が出ます。
今回は、効率の良い定期テスト対策について解説していきたいと思います。
定期テストの計画はどのように立てればいい?
定期テストは、夏休みや冬休みなどの期間をのぞいて、大体1か月から2か月くらいのスパンをあけて行われます。
そのため、テスト範囲を勉強する場合、1、2か月前に授業で習ったことを確認する必要があります。
中間テストは5教科、期末・学年末テストの場合は9教科なので勉強のペース配分を考えて効率よくやらないと時間が足りなくなってしまう可能性があります。
【定期テスト2週間前】勉強の計画を立てよう
定期テストの2週間前に各教科担当の先生からテスト範囲を教えてもらうことになると思います。
すべての教科のテスト範囲がわかったら、まずは勉強の計画を立てましょう。
とはいえ、テスト2週間前から1週間前は、部活動があるため細かく計画を立てたとしてもなかなかその通りに勉強が進まないと思います。
そのため、定期テストから1週間前までの期間については、短時間でも勉強できる暗記科目を中心に自分ができる最低限の範囲で計画を立てましょう。
スマホを持っている方は、暗記に使えるアプリを使って勉強しても良いかもしれません。
【定期テスト1週間前】苦手分野の勉強をしよう
定期テスト1週間前になると、大会が近いなど特別な事情をのぞいて、多くの学校が部活動停止期間になると思います。
そのため今まで朝練や放課後練にあてていた時間を勉強にあてることができます。
定期テスト1週間前に重点をおいてやることは、苦手分野の勉強です。
苦手分野は、応用問題まですべてカバーしようと思うと、なかなかやる気がでないと思います。
そのため、まずは基本問題を理解することに専念してください。
基本問題と応用問題を同時に勉強すると、結局どちらも身につかないリスクがあるので気を付けましょう。
【定期テスト3日前】テスト範囲にあった問題集を解く
定期テスト3日前からは、教科書を読んだり、ノートを見返したりといった勉強方法ではなく、学校で配られた問題集を解いてください。
中学校の定期テストに出てくる問題は、学校で配られた問題集を参考にして作成される可能性が高いです。
そのため、とにかく繰り返し同じ問題集を解いてください。
【定期テスト前日】必ず十分な睡眠時間をとる
定期テスト前日は、深夜まで勉強することは避けて、しっかり睡眠時間を確保してください。
睡眠が足りていない状態でテストに臨むと、思考力がにぶってしまいます。
また睡眠は勉強して覚えたことをしっかり定着させるためにも重要です。
みなさんが寝ているとき、脳は起きていたとき記憶(勉強して覚えた知識など)の情報を整理して、忘れないように記憶を定着させます。
そのため、睡眠時間を削って勉強するよりも、十分な睡眠をとってテスト本番に臨んだ方が良いのです。
【定期テスト当日の朝】早起きと朝食をとることが大切
定期テストの当日は、早起きを心がけましょう。
早起きする理由は、起きてからすぐの脳はきちんと活性化していないからです。
また、きちんと朝食をとることも大切です。
脳は夜のあいだも活動しているので、起床後の脳はエネルギーが足りない状態です。
そのため、脳のエネルギー源であるブドウ糖を体内に取り入れる必要があります。
ブドウ糖が多く含まれる食べ物は、米や小麦などの穀物類や、ブドウやバナナといった果物が挙げられます。
テストに向けて脳がきちんと働くように朝食をしっかり食べて登校してください。
【定期テストの本番】時間配分を意識する
定期テストの本番では、時間配分を意識してください。
テスト開始する前に、解答用紙が配られると思います。
解答用紙からテストに大問がいくつあるのかがわかります。
また、解答枠が狭ければ、選択問題や短文で答えられるような問題である可能性が高いです。
一方で、解答枠が広ければ、記述式の問題があると予測することができます。
テストが開始されたら、すぐに解答し始めるのではなく、まず各大問がどんな内容なのか確認してください。
そのうえで時間配分を決めましょう。
ひとつの問いにたくさん時間をかけて、後のわかる問題に手がつけられなかったという状況を回避するため、考えてもすぐにわからない問題は一度飛ばして、今自分が解ける問題を優先して解答を記入してください。
5教科の定期テスト勉強法
中学校の定期テストで必ず勉強しなければならない科目は、「国語」「数学」「英語」「理科」「社会」の5科目です。
苦手な科目があった場合、どのように勉強すればいいのでしょうか。
それぞれ確認していきましょう。
数学の勉強方法
数学の勉強方法は、基本を押さえることが重要です。
そのため、公式はうろ覚えではなくきちんと覚えてください。
学校が定期テストを行う目的は、お子さんの学習理解度です。
そのため、難しい問題がたくさん出題されるわけではなく、基本問題が出題される割合の方が高いです。
テストを作成する先生の傾向によりますが、基本問題7割、難しい問題が3割程度と考えてよいと思います。
英語の勉強方法
英語の定期テストは、大体次のような内容で構成されています。
- 1.リスニング
- 2.単語や熟語の意味を問う問題
- 3.短文を英訳・和訳する問題
- 4.長文問題
英語が苦手な場合、2の単語や熟語を暗記することから始めてください。
単語と熟語の意味が分かれば、3や4で聞かれていることが完璧でなくても理解することができます。
そのため、まずはテスト範囲に出てくる単語と熟語のスペルと意味、読み方を暗記しましょう。
また、英訳でつまずいている場合には、「主語」と「動詞」を意識して、教科書や問題集に載っている英文を確認すると良いでしょう。
また英語の長文問題が難しいと感じたときには、まず問題を確認して文章を読んでみてください。
国語の勉強方法
国語を勉強するときには、漢字と文法問題を覚えると良いと思います。
また、漢文問題も「レ点」や「一二点」のルール覚えれば、必ず点数に結び付く問題です。
古文は尊敬語や謙譲語で書かれているかによって、登場人物の誰が話しているのかなどを掴むことができます。
そのため、まずは単語や文法を中心覚えましょう。
評論文の読解に関しては、文章を読む前に問題を読むことによって答えが見つけやすくなります。
また、文中の指示語が具体的に何を指しているのかを把握することも大切です。
更に、「しかし」や「また」といった接続語の後の文章は評論文において重要な点である可能性が高いので、チェックしておくと良いでしょう。
理科の勉強方法
中学校の理科はとにかく出てくる単語を暗記することが大切です。
特に第2分野は、生物や地学に関する勉強なので覚えることが重要なのです。
とはいえただ単に記憶する作業は、お子さんによって退屈と感じる場合もあるかと思います。
また、図を用いて名称を解答するような問題もあるため、図がある問題集を使って学習した方が良いでしょう。
文章や図だけでは、なかなか覚えられないときには理科の資料集を使って、実際の写真を見てイメージを持って学習することも良いと思います。
理科の第1分野に関しては、物理や化学を学習することになります。
電流や圧力などの物理分野では計算が必要になります。
また、化学の分野のテストでは化学反応式を解く必要があります。
第1分野は、得意・不得意が大きく分かれる分野で、第2分野で高得点がとれるお子さんでもつまずく可能性のある分野です。
勉強方法は、できるだけ問題集を解くこと、また第2分野と同様イメージがつかないときには資料集で実際の写真や画像を確認することが大切です。
社会の勉強方法
中学生の社会は、地理・歴史・公民に分けることができます。
いずれも暗記が重要です。
地理のテストについては、世界や日本の地域の気候や地形、産業等が出題されます。
そのため、一問一答のような問題集で用語を覚えることが大切です。
歴史については日本史を重点的に世界史も勉強します。
テストの出題傾向としては、年表で覚えるよりも、歴史の流れを掴むことが大切です。
単に用語として覚えただけですと、年代順の並び替えの問題や、歴史的事件の内容について出題された場合、解答できなくなってしまいます。
また、年代を覚えるよりもそれぞれの歴史的な出来事を関連付けて学習した方が、記憶に残りやすくなります。
公民は、多くの場合中学校3年生で学習します。
具体的な学習内容は、日本の経済や政治、法制度の仕組み、戦後から現代にいたるまでの歴史等が出題されます。
公民のテストは範囲によって大きく異なりますが、暗記で点数を稼ぐことは可能です。
しかし、暗記といっても憲法の穴埋め問題なども予想されるので、教科書から流れを確認しつつ、重要なキーワードはなんなのかを念頭にいれ勉強する必要があります。
まとめ
今回は、中学生の定期テスト対策について解説していきました。
定期テストは、内申点に関わる重要なものです。
また、学習した時期にきちんと勉強することによって、長期記憶として脳に残り、高校受験の際にも、その知識が役立ちます。
とはいえ、自力でテスト勉強を行うのは難しいと思う方もいるかもしれません。
そんなときは、一度塾に入って講師に教えてもらうことも考えてみてください。
公開日:2022-09-30 /更新日:2022-10-05
 自分にあう教室を探そう!
自分にあう教室を探そう!